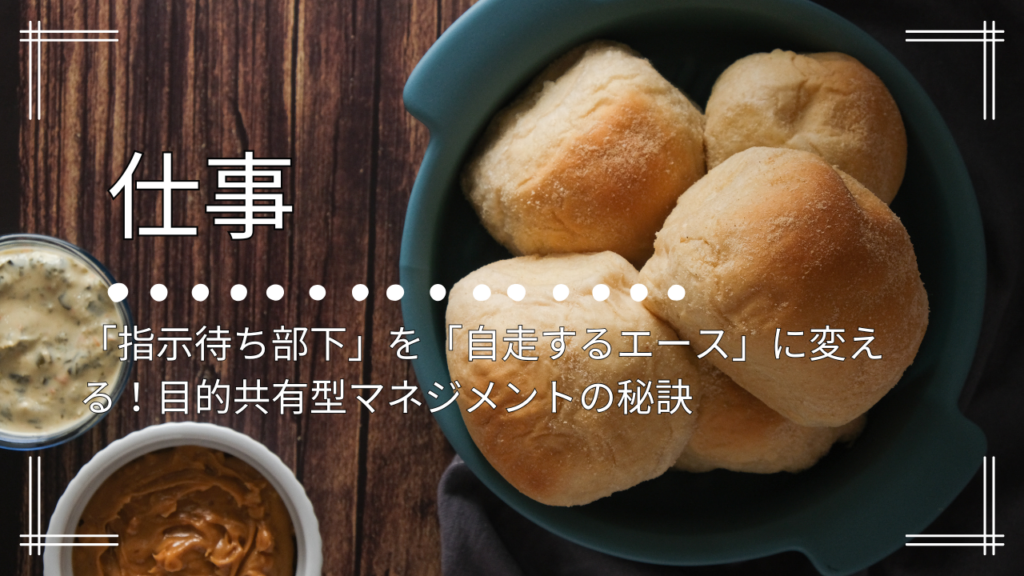
「部下が指示したことしかやってくれない…」 「もっと自分で考えて、主体的に動いてほしいのに…」 「細かく指示を出さないと不安。でも、それだと自分がいくら時間があっても足りない…」
チームを率いる立場にある多くの方が、メンバーの「指示待ち」の姿勢に一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。しかし、その受け身の姿勢は、もしかしたら日々のマネジメントスタイル、特に指示の出し方によって、知らず知らずのうちに助長されているのかもしれません。
今回は、メンバーの思考停止や依存心を生みやすい管理方法の問題点を掘り下げ、メンバー一人ひとりの主体性と能力を引き出すための、より効果的な働きかけ方について考えていきます。
過度な指示・管理が生む弊害
メンバーのミスを防ぎたい、あるいは効率を重視するあまり、上司やリーダーが仕事の手順や方法を細部まで指定し、その実行を厳しく管理・統制するというアプローチを取ることがあります。一見、丁寧で確実な方法に見えますが、この「命令と統制に基づいた管理」が行き過ぎると、チームや組織にいくつかの深刻な問題を引き起こす可能性があります。
- 思考停止と指示への依存: 常に「何を」「どのように」やるかまで細かく指示されると、メンバーは自分で考えることをやめてしまいます。「指示通りにやること」が目的化し、指示がなければ動けない、あるいは指示された範囲以上のことをしようとしない、思考停止状態に陥りやすくなります。
- 変化への対応力の低下: 予期せぬ問題が発生したり、状況が刻々と変化したりする現代において、現場で対応が必要になった際、指示がないために行動が遅れてしまいます。上司の判断や指示を待つ時間が、ビジネスのスピード感を損ない、機会損失や問題拡大に繋がります。
- 成長機会の損失とモチベーション低下: メンバーは指示された作業をこなすだけの「作業者」になってしまい、より良い方法を模索したり、創意工夫を発揮したりする機会を失います。これは能力向上の機会損失であると同時に、「やらされ感」を生み、仕事への意欲(モチベーション)を低下させる原因にもなりかねません。
- 誤った指示の実行リスク: メンバーが「指示はおかしい」あるいは「もっと良い方法がある」と気づいたとしても、それを指摘したり、自ら修正したりすることをためらいます。結果として、明らかに非効率、あるいは間違っていると分かっている指示でも、そのまま実行されてしまうリスクが高まります。
このように、細かすぎる指示と管理は、短期的には統制が取れているように見えても、長期的にはメンバーの主体性を奪い、組織全体の活力を削いでしまう危険性をはらんでいるのです。
主体性を育む「目的共有・裁量委任」のアプローチ
では、どうすればメンバーの主体性を引き出し、自ら考えて動けるチームを作れるのでしょうか。その鍵となるのが、「目的や方針を共有し、現場に裁量を委ねる」というアプローチです。
これは、上司が仕事の「やり方」を細かく指示する代わりに、
- 仕事の「目的」や「背景」(なぜやるのか?)
- 達成すべき「目標」や「期待される成果」(何を目指すのか?)
- 守るべき「制約条件」や「組織としての方針」
といった大枠を明確に共有し、その目標達成のための具体的な「実行方法(どのようにやるか)」については、メンバー自身の判断や工夫に任せるという考え方です。
このアプローチがうまく機能すると、以下のような効果が期待できます。
- 柔軟性とスピードの向上: メンバーは与えられた裁量の範囲内で、現場の状況に合わせて最適な方法を判断し、実行できます。これにより、状況変化に対して、いちいち指示を待つことなく迅速かつ柔軟に対応できるようになります。
- 主体性と当事者意識の向上: 「どうやるか」を自分で考えるプロセスを通じて、仕事への当事者意識が高まり、責任感を持って主体的に取り組むようになります。
- 能力開発と成長: 試行錯誤しながら仕事を進める中で、問題解決能力や判断力、専門スキルなどが磨かれ、メンバー自身の成長に繋がります。
- より良い成果の可能性: 現場をよく知るメンバーが自ら考えることで、上司が想定していなかったような、より効果的な方法や革新的なアイデアが生まれる可能性も高まります。
単なる「スタイル」ではない、機能させるための要点
ただし、「目的を伝えて任せる」というスタイルは、単に「丸投げ」するのとは全く異なります。このアプローチを真に機能させ、チームと個人の成長につなげるためには、いくつかの重要な要素があります。
- 状況に応じた使い分けの重要性: メンバーの経験、スキルレベル、タスクの性質(定型業務か、新規性の高い業務か)、緊急度などに応じて、指示の具体度や裁量の範囲を調整することが現実的であり、効果的です。常に同じスタイルではなく、状況に合わせたリーダーシップ(状況対応型リーダーシップ)が求められます。
- 「なぜ」を伝えることの価値: 目的や目標を伝える際には、「何を」だけでなく「なぜ」それが必要なのか、その仕事が組織全体の中でどのような意味を持つのか、といった背景情報を丁寧に共有することが極めて重要です。この「なぜ」への理解が、メンバーが適切な判断を下すための拠り所となります。
- 心理的安全性の確保: メンバーが安心して自分の意見を表明したり、新しい方法を試したり、あるいは失敗から学んだりするためには、**「失敗しても非難されるのではなく、学びの機会として捉えられる」という組織文化(心理的安全性)**が不可欠です。これがなければ、裁量を与えられても萎縮してしまい、結局は指示待ちに戻ってしまう可能性があります。
- 適切な関与とフィードバックループ: 権限を委任することは、決して「放置」ではありません。定期的な進捗確認、困ったときの相談への対応、結果に対する適切なフィードバックなど、マネージャーによる適切な関与とコミュニケーションは依然として重要です。ただし、その関与は「マイクロマネジメント」にならないよう注意が必要です。
- 人材育成の視点: メンバーに裁量を委ねることは、単に仕事を効率化する手段ではなく、メンバーの能力を引き出し、育てるための重要な投資であるという視点を持つことが大切です。
最後に
メンバーの主体性を奪い、指示待ちの状態を生み出してしまう「命令と統制に基づいた管理」と、メンバーの自律性と成長を促す「目的共有・裁量委任」のアプローチ。どちらが長期的にチームや組織にとって有益かは明らかでしょう。
もちろん、後者のアプローチを実践するには、明確な方針設定、メンバーへの信頼、そして丁寧なコミュニケーションが不可欠であり、マネージャーにはより高度なスキルが求められます。しかし、その努力は、メンバー一人ひとりが自ら考え、動き、成長していく「自走するチーム」という、大きな成果となって返ってくるはずです。
もし、あなたが現在のチームの状況に課題を感じているなら、一度立ち止まり、ご自身のマネジメントや働きかけのスタイルを見つめ直してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。










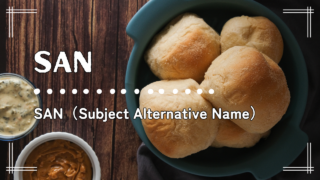



コメント